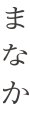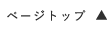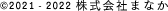石櫃に平穏をみる
17. 8 / 4
[ コラム ]

京都の日本庭園で奈良時代の石櫃(いしびつ)をみる機会があった。
石櫃とは火葬された遺骨を収めた骨壷をさらに収める容器で、墓石の原基のようなものといえば想像できるだろうか。その印象は、決して遺産めいた厳しいものではなく、姿形がこんもりとしていて、とても愛らしい印象だった。
石櫃は庭園の植物とよく馴染んでいて、しばらく眺めていると穏やかな気持ちになる。それまで気に掛けなかった風の音や、鳥の鳴き声まで聞こえてくるようになる。不思議と身体が徐々に感覚を開きながら、どんな微細なものでもすべてを感受しようとしているように思えてくる。
すると、見ている光景と湧き上がった気持ちの、いわく言い難いこの交わりを、端的に表したことばを思い出した。江戸時代の国学者・本居宣長(1730〜1801)が説いた「もののあはれ」である。
「もののあはれ」とは、喜怒哀楽のあらゆる感情「あはれ」が、万物「もの」に触れ交わることで、固有の美意識を獲得していくこと、であった。この「もののあはれ」がおもしろいのは、感情を指す「あはれ」も、万物を指す「もの」も、はっきりとした輪郭を限定せず、先の石櫃の光景のようにあらゆるものの境界を曖昧にし、しかし一体となることをあらわにすることばとして用いられているところである。
言い換えれば、この世界と知覚するわたしの認識論であり、日本人がはじめて構築した 「情動の哲学」であった、ともいえるだろう。
実は人類学的にみても墓石や墓標は、碑(いしぶみ)であっても実用性はないらしい。
たとえば北米民族のトーテムや、南アフリカの少数民族に残る原住民の背丈よりはるかに大きい墓標などは「死者への鎮魂を天空高く届ける」という意味があるのだと聞いた。日本でも沖縄では、亀甲墓(カミヌクーバカ)という古来のお墓が残っていて、一説には「回帰」を意味する女性の子宮を象(かたど)っているともいわれている。
人生には避けられない数々の苦悩があり、中でも死別は身を切られるほど哀しい。
宣長が「もののあはれ」の原理の中に、美しさと悲哀を共生させたのは、平穏や慰めなどの内なる救済や浄化までを包括しそこに見ていたからではなかったか。
石櫃の中には眠る者がいて、時を経てもその光景に平穏をみたわたしがいる、というように。